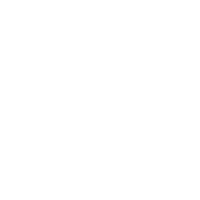重要無形文化財 十四代酒井田柿右衛門本人作の一輪生を譲り受けました。
本人作のお品物は稀にしか出会わないので柿右衛門の基本絵付色にちなんだ背景紙を用意し撮影しました。
濁手と呼ばれる柔らかく温もりある乳白素地に繊細な筆使いで絵付がほどこされています。
以前、この濁手(にごしで)という文字と綺麗な乳白色が結びつかなく、??となったことが思い出されます。
濁手とはお米のとぎ汁に例えられつけられた名前です。

基本色は赤・緑・群青・紫・黄です。濁手にとても映える絵付色。
十七世紀に確立された柿右衛門様式と呼ばれる色彩と図案構成はマイセンなどのヨーロッパ陶磁器にも大きな影響を与えました。



本人作の濁手を見て「柿右衛門の基本絵付色の背景紙で撮影すると濁手はどのように見えるのか?」と思いつき撮影してみました。
図録などの作品写真の背景は白・灰・黒色くらいしかないので、ちょっと目新しい柿右衛門の写真になったかと思います。
濁手が背景色を優しく反射してくれました。個人的には最後の薄紫が絵付・濁手と一番マッチしていると思います。
丁寧な査定と明朗会計をお約束。骨董品・美術品・時代物の売却は高価買取の当店にお任せください。
ORIGENでは骨董品を中心に美術品から時代物まで幅広いお品ものを取り扱いしております。
どんなお品ものでも拝見いたします。
お品ものの買取や売却に関してのご相談はお電話またはメールフォーム・LINEよりご相談ください。
よろしくお願いいたします。
買取のご依頼・商品のお問い合わせは06-7509-5761までお気軽にお電話ください。
お手軽なLINEでのお問い合わせはこちらから簡単にトーク画面にアクセスできます。
メールフォームからのお問い合わせはこちらからお気軽にご相談ください。
出張買取エリア:大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山を中心に全国に対応いたします。
弊社では近畿・中部・中国地方をはじめ、ご相談に応じて全国に出張いたします。
大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山は最短で当日にお伺いが可能です。
お所に関わらず、お気軽にご相談ください。