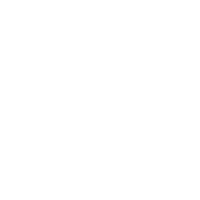「古くなった実家。空家になり、片付けないと。と思いながらも早5年。。。
思うように手が進まず、時間だけが過ぎてしまいました。見に行く度に傷んでいく実家。
今年こそ処分したいと考えています。ご相談させていただいてもいいでしょうか。。。」
毎年、ご相談件数が増えている空家整理に伴う出張買取りのご相談。
何から手をつけていいのか悩んでしまい、片付けが一向に進まず、
気づけば数年もの歳月が経過してしまった。
という方も少なくありません。
「全て廃棄してしまおうか、、でも誰か使ってくださる方がいるかも、、
売れるかな、、売れないか。。。勿体ないなぁ。。。」
築年数の古いお家であればあるほどに長い年月をかけて溜め込まれた品々が大量にあり、
親や祖父母の残したものの思い出を整理しながら思い入れのある品を探したり、
価値あるものを探したりしなければなりません。
ただでさえ忙しい日常生活に加え、
物を大切にしたいと考えておられる故に時間が掛かってしまう状況。
よく分かります。

実は長い時を経たものを短い時間できちんと仕分けするのはとても気を遣います。
じっくり見る余裕のない査定は、どうしても見落としなどしやすいため
ぜひゆとりがある状況が望ましいです。
ですが実際はみなさま色々なご事情があり、
時間が全くないという方からのご相談も少なくありません。
急な不動産売却やお引越しに伴う家財品の整理で1週間以内に査定してほしいといった案件から、
なんと「今日明日中に査定して全て引き取ってほしい」というタイトなご依頼も。
そのような場合でも遠慮なくご相談ください。
可能な限り迅速にお伺いして細かく丁寧な査定をさせていただきます。
・どこに相談していいのか判らず、時間を掛けて業者を探されている方
・急な依頼でどこの業者さんにも査定・引取りを断られてしまった方
・一度、別の業者さんに見てもらったけれど少ししか引き取ってもらえなかった方
など、同じ想いや経験をお持ちの方が沢山居られるかと思います。
ORIGENではご相談内容に応じて適切な査定ができるように努めておりますので、
いつでもお気軽にご相談ください。
丁寧な査定と明朗会計をお約束。骨董品・美術品・時代物の売却は高価買取の当店にお任せください。
ORIGENでは骨董品を中心に美術品から時代物まで幅広いお品ものを取り扱いしております。
どんなお品ものでも拝見いたします。
お品ものの買取や売却に関してのご相談はお電話またはメールフォーム・LINEよりご相談ください。
よろしくお願いいたします。
買取のご依頼・商品のお問い合わせは06-7509-5761までお気軽にお電話ください。
お手軽なLINEでのお問い合わせはこちらから簡単にトーク画面にアクセスできます。
メールフォームからのお問い合わせはこちらからお気軽にご相談ください。
出張買取エリア:大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山を中心に全国に対応いたします。
弊社では近畿・中部・中国地方をはじめ、ご相談に応じて全国に出張いたします。
大阪・奈良・兵庫・京都・滋賀・和歌山は最短で当日にお伺いが可能です。
お所に関わらず、お気軽にご相談ください。